
|
|
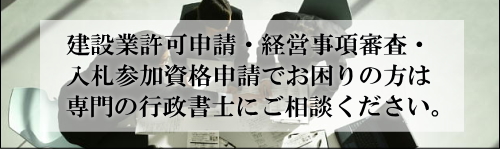

経営業務の管理責任者とは?
経営業務の管理責任者の要件が求められるのは以下のような理由からです。
建設業を経営するには、受注した工事それぞれの事例に応じ、
資金調達、資材購入、技術者や労働者の配置、下請業者の選定や契約締結、
施行管理や、現場周辺住民との調整などを行う必要があります。
いくら、すぐれた技術を有していても、この様な資金繰りや労務管理、
関係者との連絡調整など多岐の渡る、経営の経験を持っていないと、
その業者さんは倒産に陥る可能性が高くなってしまいます。
倒産に至った場合、建設工事1件あたりの請負金額は高額であることが多く
その注文者にあたえる影響は計り知れません・・・。
そのため、
許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、
個人で営んでいる場合には、事業主本人または支配人のうちの1人が
経営業務の管理責任者になるための要件を備えた者であることが、
建設業許可を取得する上で求められるのです。
経営業務の管理責任者になるには、
法人の役員(※1)、個人の事業主、支配人(※2)、令3条の使用人(※3)など
営業取引上、対外的に責任を有する地位にあるものとして、
資金や資材の調達、技術者の配置、下請業者の選定、労災の防止、周辺の住民への対応など建設現場における施行監理全般など、建設業を営むうえで必要な経営業務についての経験が
許可を受けようとする業種で5年以上、
許可を受けようとする業種以外の業種で7年以上
あることが必要です。
また、
経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、執行役員としての経験(※4)、
経営業務を補佐した経験(※5)がある者も経営業務の管理責任者になることが
認められるケースもあります。
※1 経営業務の管理責任者になることが出来る、「法人の役員」とは
経営業務の管理責任者になることが出来る法人の役員とは
建設業の主たる営業所(本社や本店など)に常勤し、以下のものとして登記されている方です。
株式会社や特例有限会社の取締役
委員会設置会社の執行役(執行役員ではありません。)
合名会社や合資会社の無限責任社員
合同会社の有限責任社員
事業協同組合の理事
なお、以下の者は経営業務の管理責任者なることが出来る法人の役員に含まれません。
監査役、監事
合同会社の有限責任社員
事務局長 など
また、
建築士事務所の「管理建築士」や宅地建物取引業者の「専任の宅地建物取引主任者」など
他の法令で専任を要するものは、常勤で勤務している事業体および営業所が同一であ場合は兼任することが出来ます。
※2 経営業務管理責任者になることが出来る、「個人の事業主・支配人」とは?
「個人の事業主」とは、確定申告書における事業主を指し、
受付印のある確定申告書の控えや、所得証明、工事請負契約書などで、
許可要件である、5年又は7年以上の経験を証明します。
「支配人」とは、商業登記法上の支配人登記が行われ、個人事業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上、又は裁判外の行為をする権限を有する使用人のことをいいます。
※3 令第3条の使用人とは
建設業の許可を取得している建設業者が、支店などの「従たる営業所」を設置する場合に、その営業所での請負契約の見積もり、入札、契約締結などの一定の権限を会社の代表者から委任された事実上の責任者のことです。
具体的には、営業所長、支店長などが該当します。
※4 執行役員としての経験とは
取締役会設置会社において、許可を受けようとする建設業に関する事業部門に関して、業務執行権限の委譲を受ける者として、選任され、且つ、取締役会によって定められた業務執行指針に従って代表取締役の指揮及び命令のもとで具体的な業務執行に専念した経験をいいます。
この執行役員としての経験が、5年以上有り、経営業務の管理責任者として申請する時には、常勤の役員に就任している場合、経営業務の管理責任者になることが出来ます。
定款や執行役員業務分掌規定、取締役会議事録などで、経験の内容を、
請負契約や経営業務に関する決裁書で経験期間を証明します。
※5 経営業務を補佐した経験とは
法人の場合
営業部長、工事部長など管理職以上の地位に有り、経営業務の執行に関して、取締役に準ずる権限を有する者が許可を受けようとする建設工事の施工に必要とされる、資金調達、技術者配置、下請業者との契約締結など経営業務に関して総合的に管理した経験をいいます。
この経験が、7年以上あれば、経営業務の管理責任者になることが出来ます。
辞令、職制図、職務分掌表などで経験の内容や期間を証明します。
個人の場合
元々は事業主の死亡などによって、実質的に廃業されるのを救済する場合に限って適用されていた基準でしたが、静岡県知事許可においては、平成24年11月よりその要件が、若干緩和されました。
個人の建設業許可業者が事業を廃業し、前事業主の許可番号を引継ぐ事業承継をする場合は、
従前と同様に、7年以上、前事業主の建設業の経営業務を補佐した経験のある配偶者または子(孫は該当しません)に限られます。
独立開業し新たに許可を申請し許可番号を新たに取得する場合や、他の建設業者の役員や支配人に就任し、経営業務の管理責任者になる場合は、血縁関係を問わず、建設業の経営業務を補佐した経験があるものとして認められます。具体的には、前事業主のお孫さんや、前事業主の片腕として頑張っていた番頭さんなどが該当することになります。
但し、個人事業主の補佐経験により「経営業務の管理責任者」になろうとする場合は、原則として、個人事業主1人につき、1名のみ補佐経験者として認定されることになっていますので注意が必要です。
前事業主の税務上、建設法上廃業届にて全事業が廃業していることを証明し、
確定申告書の写しの専従者欄や給与欄などで、経験期間や前事業主に次ぐ職制上の地位を
工事請負契約書や建設業の許可申請書などで、工事請負の経験を
許可番号を引継ぐ事業承継を行う場合、前事業主の除籍謄本にて全事業主の死亡を
申請者の戸籍謄本にて、建設業許可の許可申請者と前事業主との関係(配偶者または子か?)
前事業主の最終の貸借対照表、損益計算書及び、承継時の開始貸借対照表にて建設工事における債権債務が承継されていることを証明します。
|

