
|
|
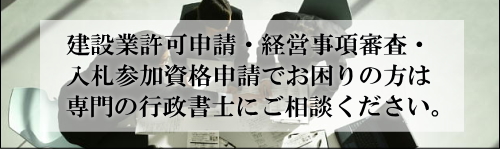
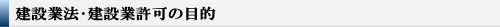
建設業法は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正な施行を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的として定められた法律です。
建築物や土木工作物は、手抜き工事があっても通常はある程度の年月が経たなければ、手抜き工事であるか否か判断できないものです。
そのため、工事の発注者が、一定の基準を満たし、適正な施行を行うことが出来る建設業者を選び、手抜き工事を未然に防ぐことを目的として建設業の許可制度が定められました。
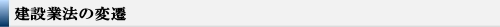
終戦後、戦災復興により建設需要が急増し建設業者の数も急増しました。しかし昭和22年頃からは、急速に工事量は減り、熾烈な過当競争を生む結果となりました。経営難による請負価格のダンピングは、手抜き工事、下請いじめ、前渡金の詐取等の悪質業者の増加を招き建設業界全体の信用が失われていきました・・・。
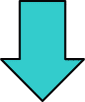
昭和24年 建設業法の成立
概要
①目的 建設業を営む者の登録の実施し、工事の適正な施行確保すること。
②請負契約の公正な履行確保のため請負契約の原則を定めた。(一括下請負禁止など)
③工事現場、各営業所に一定の技術者を置かなければならないこと等について規定された。
④建設業に関する重要事項を審議する機関として、建設業審議会が設けられた。
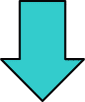
昭和46年 建設業の近代化、合理化を目的とした大改正
概要
①建設業許可および特定建設業許可制度の採用
②下請人の保護規定の新設
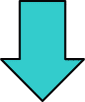
昭和62年 公共工事、建設投資の減少による、競争激化、不良業者増加に対応する改正
概要
①特定建設業の許可基準の改正
②監理技術者制度の整備
③技術検定の指定試験機関制度の導入
④経営事項審査制度の整備
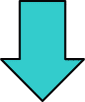
平成6年 公共工事をめぐる不祥事多発に対する、入札・契約制度の改革を目的とした改正
概要
①許可要件(欠格要件)の強化
②公共工事を発注者から直接受注する建設業者は経営事項審査を受審することとした。
③特定建設業者の施工体制台帳、施工体系図の整備
④監理技術者の専任性の徹底、主任技術者と監理技術者の職務の明確化
⑤帳簿の備付
⑥監督の強化
⑦許可の簡素合理化・・・許可の有効期限を3年から5年に延長
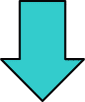
平成18年 構造計算書偽装事件をふまえ、建築士制度の見直しと併せて行われた改正
①元請責任の徹底
②技術者の資質の向上
③施工に関する記録の保存
④紛争解決手続きへの時効中断効の付与
⑤工事監理に関する報告
|

